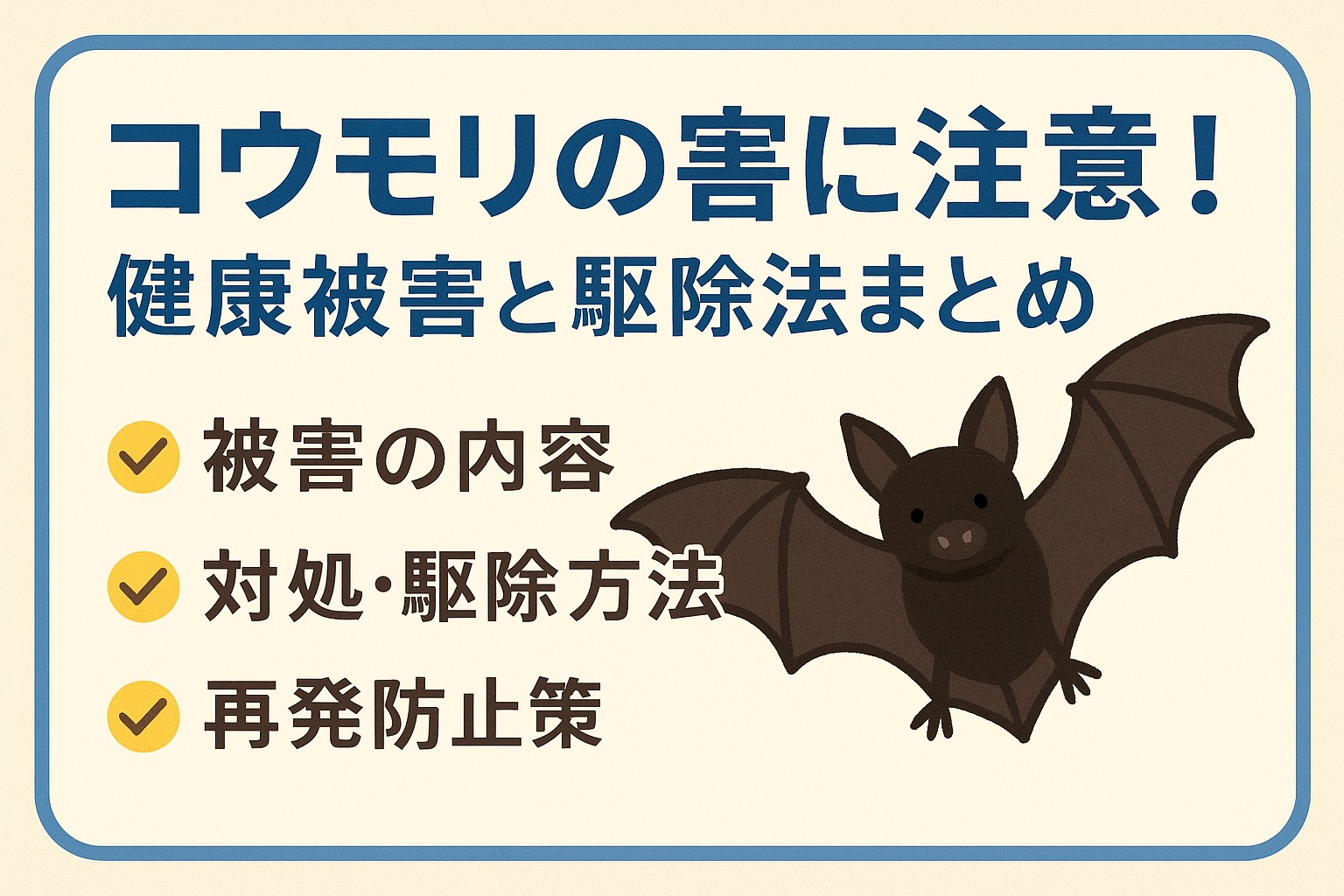
最近、「夜になると天井裏で音がする」「ベランダに糞のようなものが落ちている」といった相談が増えています。
実はこれ、コウモリが原因かもしれません。以前は山間部や自然の多い地域で見られていたコウモリも、今では都市部の住宅地にまで現れるようになっています。
コウモリは見た目が小さく無害に思われがちですが、実は健康や建物に深刻な害をもたらすことがある厄介な存在です。
糞尿による汚染や騒音被害に加え、ウイルスやダニなどによる健康リスクも無視できません。
この記事では、コウモリによる被害の実態から、正しい対処法、効果的な駆除方法、そして再発防止のための予防策までを幅広く解説していきます。
知らずに放置すると被害が拡大することもあるため、早めの理解と行動が大切です。
記事のポイント
●コウモリがもたらす健康被害や建物への悪影響について理解できる。
●家に侵入する原因や住みつきやすい場所が分かる。
●自分でできる追い出し・駆除方法とその注意点が分かる。
●再発防止や業者に依頼する必要性とタイミングが理解できる。
コウモリはなぜ害獣なのか?
一見、小さくて可愛らしい印象のあるコウモリですが、実は住まいに入り込むとさまざまな害を及ぼすことがある厄介な動物です。
近年では住宅街でも目撃が増えており、被害の相談も多く寄せられています。ここでは、なぜコウモリが「害獣」とされるのか、その理由を具体的にご紹介します。
糞尿による悪臭・カビ・腐食の被害
コウモリが屋根裏や換気口などに住みつくと、まず問題になるのが糞尿です。特にフンは量が多く、蓄積すると強いアンモニア臭を放ちます。
この臭いが室内にまで広がることで、生活に大きなストレスを与えるだけでなく、体調不良の原因にもなりかねません。
さらに、湿気を含んだフンは建材を腐食させ、天井や壁にシミやカビを発生させることもあります。これが長期化すると修繕費用も高額になり、放置するほど被害は深刻になります。
鳴き声や夜間の活動音によるストレス
コウモリは夜行性のため、活動するのは主に夜間です。飛び回るときの羽ばたきや鳴き声が屋根裏から響き、睡眠の妨げになったという声もよく聞かれます。
特に小さなお子様や高齢者がいる家庭では、夜中の音に悩まされているケースも少なくありません。
また、複数の個体が住みついた場合には騒音も大きくなり、精神的な負担が増す傾向にあります。日常の静けさを取り戻すためにも、早めの対策が必要です。
「縁起がいい」は本当?スピリチュアル的な誤解
日本では昔から「コウモリは福をもたらす」「縁起のいい動物」といった言い伝えがあり、特に中国文化ではその傾向が強く見られます。そのため、迷信的な考えから放置してしまう方もいます。
しかし現実には、家に住みついたコウモリは健康や建物に明確な害を与える存在です。
「縁起がいいから大丈夫」と見過ごすことは、かえって被害を広げる原因になってしまいます。迷信と現実を切り分け、冷静に対応することが大切です。
このように、コウモリは自然の中では有益な役割も担っていますが、人の生活空間に入り込んでしまうと一転して害獣となってしまいます。
被害を防ぐには、まずその実態を正しく理解することが第一歩です。
害獣害虫駆除なら「あい営繕」にお任せ!!
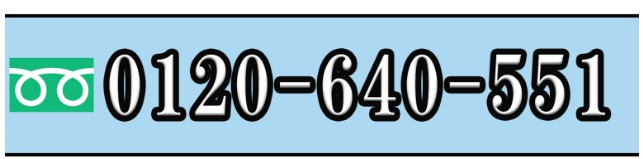 無料で現地調査、見積りを行います。
無料で現地調査、見積りを行います。
年中無料、8:00から20:00 フリーダイヤルでお気軽にご相談下さい。
(福岡県全域、山口県西部、佐賀県東部)
健康被害のリスクとは?
コウモリがもたらす害は、建物や生活環境への影響だけではありません。
もっとも注意すべきなのは「健康被害」です。見た目では無害に見えるかもしれませんが、実際には人間の健康にとって深刻なリスクをもたらす存在です。
病原菌・ダニ・ウイルスを媒介する危険性
コウモリの体や巣には、目に見えない病原体や寄生虫が潜んでいます。
代表的なものとしては、細菌性の感染症やウイルス性感染症、日本脳炎ウイルスなどが挙げられます。
特にコウモリのフンや尿は乾燥すると空気中にまき散らされ、それを吸い込むことで体内に入ってしまう可能性があります。
また、コウモリにはダニやノミが寄生していることもあり、それが人間の居住空間にまで広がってしまうこともあります。
皮膚トラブルやアレルギー症状の原因になることもあるため、見かけたらすぐに掃除すればいいという簡単な話ではありません。
咬傷や接触による直接的なリスク
インターネット上の掲示板や知恵袋などでも、「寝ていたらコウモリに噛まれた」「素手で捕まえたら引っかかれた」といった書き込みが見られます。
実際に日本ではコウモリが人に噛みつくケースは非常にまれではありますが、まったくゼロとは言い切れません。
特に屋根裏に住みついたコウモリを追い出そうとして、驚いたコウモリが飛び出してきて接触する…といったパターンもあります。
たとえ小さな傷でも、そこから細菌が入り込むリスクがあるため、油断は禁物です。
なぜ「コウモリを触ってはいけない」のか?
「コウモリを見つけたら素手で触らないで」と言われるのには、はっきりとした理由があります。それは、先に述べたように病原体や寄生虫の存在が確認されているからです。
さらに、世界的にはコウモリを媒介とした狂犬病ウイルスの感染例も報告されており、絶対に軽視してはいけません。
日本では狂犬病の発生はほぼありませんが、海外ではコウモリからの感染例があることからも、慎重な対応が必要です。
たとえ死んでいるように見えても、触れることで感染源になる可能性はゼロではないのです。
このように、コウモリに関する健康被害は「見えにくいけれど確実に存在するリスク」です。子どもや高齢者がいる家庭では特に注意が必要です。
気になる気配を感じたら、自己判断せずに専門業者に相談するのが安全な選択と言えるでしょう。
家に侵入する原因と住みつきやすい場所
コウモリが家に入り込むのは、偶然ではありません。実は住宅の構造や周辺環境が影響していることが多く、特に住みつきやすい条件がいくつかあります。
ここでは、コウモリがどこから侵入し、どんな場所に定着しやすいのかを見ていきましょう。
狙われやすいのは「屋根裏・換気口・シャッターの隙間」
コウモリは非常に小さな隙間からでも入り込むことができます。
多くの家で被害が報告されているのは、屋根裏、換気口、エアコンの配管周辺、雨戸の収納スペース、そしてシャッターの隙間などです。
これらの場所は高所にあり、人の目が届きにくいため、コウモリにとって格好のすみかとなります。
わずか2cm程度の穴でも侵入できると言われており、「これくらいの隙間なら大丈夫」と思っていても、すでに住みつかれているケースも珍しくありません。
コウモリが家を選ぶ理由とは?
コウモリが住宅に近づく理由にはいくつかあります。
まず、夜行性であるため、暗く静かな環境を好むという点。屋根裏やシャッターボックスの中は、外敵がいないうえ、温度や湿度も安定しており、コウモリにとっては非常に安心できる場所です。
また、住宅街には餌となる虫(特に蚊や小さな昆虫)が多く集まるため、食料が豊富なのも理由の一つです。夜間に灯りの周りを飛び回るコウモリを見かけることがあるのは、このためです。
被害が多い家の特徴と地域的傾向
被害が多いのは、築年数の古い木造住宅や、屋根裏の通気性が良い家です。特に瓦屋根やモルタル外壁の家は、劣化によって隙間ができやすく、侵入されやすい傾向があります。
地域別で見ると、コウモリの生息が多いのは温暖で湿度が高いエリア。日本では九州・関西・関東南部などで特に被害が多く報告されています。
これらの地域は冬でも比較的暖かく、コウモリが冬眠せず活動し続けるケースもあります。
このように、コウモリは「住みやすい環境」をしっかりと選んで入り込んできます。気づかないうちに住みつかれてしまわないよう、定期的に屋根や換気口まわりを点検することが大切です。
住宅の構造や周辺環境を把握し、侵入を防ぐ意識を持つことが、被害を未然に防ぐ第一歩になります。
自分でできる追い出し・駆除方法
コウモリの被害が発生しても、すぐに業者を呼ぶ前に、自分でできる対策を講じたいと考える方は多いと思います。
ここでは、家庭でも取り組める追い出し・駆除の方法についてご紹介します。ただし、法律や安全性に十分配慮することが前提です。
超音波グッズ・忌避剤で追い出す方法
市販のコウモリ対策グッズには、超音波を使って不快な環境を作り、コウモリを近づけにくくするものがあります。
コウモリは人間には聞こえない高周波に敏感で、特定の周波数の音を発する機器を嫌います。これらはコンセントに差し込むだけで使えるタイプが多く、比較的手軽に導入できます。
また、スプレータイプやジェルタイプの忌避剤も有効です。
これらはコウモリが嫌う成分(ハーブや天然由来の成分)を含み、侵入口や棲みついている場所に使用することで、自然と出ていくことを促します。
ただし、即効性は期待できないため、数日〜数週間の継続使用が前提です。
巣や糞の処理と注意点
コウモリを追い出すだけでは不十分です。巣が残っていたり、糞尿が放置されていると、また戻ってくることもあります。
巣の撤去や糞の清掃は徹底して行いましょう。ただしここで注意すべきなのは、衛生面と安全面です。
糞には細菌や寄生虫が含まれている可能性があるため、掃除の際は必ず防護マスク、手袋、長袖の服を着用しましょう。
また、取り除いた後は除菌スプレーでの処理や、消臭対策もしっかり行ってください。吸い込みを避けるため、掃除機の使用は避け、できるだけ拭き取り式が望ましいです。
天敵や光・音を活用した予防
コウモリは明るい場所や人の気配を嫌うため、光や音を利用して寄せ付けにくくする方法もあります。
夜間にLEDライトを当てたり、ラジオなどの音を小さく流しておくことで、居心地の悪さを感じさせることができます。
また、天敵とされるフクロウや蛇の「置物」を設置して、心理的な威嚇を与えるのもひとつの方法です。実際に動物を使うことはできませんが、最近ではリアルな作りの模型も多く出回っています。
ただし、これらの対策は「一時的な追い出し」には効果があるものの、根本的な解決にはならないこともあります。侵入経路をふさぐなどの防止策と組み合わせることが、再発防止には欠かせません。
自分でできる範囲で対応するのはとても大切ですが、被害が広がっていたり、安全面に不安がある場合は、無理をせず専門業者への相談も検討してみてください。
正しい知識と方法で、コウモリ被害をしっかり防ぎましょう。
コウモリ駆除はプロに頼むべき?
コウモリの被害に気づいたとき、「まずは自分で追い出せないか」と考える方も多いかもしれません。
しかし、実際には法律や安全面の問題があり、安易な対応はかえってリスクを高めることになります。ここでは、コウモリ駆除を業者に依頼すべき理由と、費用やタイミングの目安について解説します。
鳥獣保護法の規定に注意
日本では、コウモリは「鳥獣保護管理法」という法律によって保護対象とされています。
つまり、むやみに捕獲・殺傷することは禁じられており、違反すれば罰金や刑罰の対象となることもあるのです。
特に繁殖期(春〜初夏)には注意が必要で、駆除や追い出しを行うにも許可が必要な場合があります。
そのため、コウモリを物理的に捕まえたり、巣を破壊したりする行為は、専門的な知識がない限り控えるべきです。
プロに任せるメリットとは?
まず第一に、業者は法律に準拠した方法で作業を行ってくれます。高所での作業や屋根裏の点検も安全に対応できる装備や知識があり、一般の方が行うよりもはるかに効率的で確実です。
また、多くの業者は「再発防止」までを含めたトータルなサービスを提供しており、侵入口の封鎖や清掃・消毒など、見えない部分まできちんと対応してくれます。
一度の施工で安心できる環境を整えられるのは、プロならではの強みです。
費用の相場と依頼のタイミング
コウモリ駆除の費用は、作業の範囲や建物の構造によって異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。
-
調査費用:無料〜5,000円前後
-
追い出し作業のみ:1〜3万円程度
-
清掃・消毒・再発防止を含むプラン:3〜8万円程度
「高い」と感じるかもしれませんが、自力での対処で被害が広がった場合、修繕費用がより高額になることもあります。
気になる兆候が出た時点で、早めに相談することで被害を最小限に抑えることができます。
無理に自分で対処しようとせず、法令遵守と安全確保のためにも、プロの力を借りることが最善の選択です。
コウモリは放っておくと長期間住みついてしまうこともあるため、「おかしいな?」と思ったら、まずは専門業者に相談することをおすすめします。
害獣害虫駆除なら「あい営繕」にお任せ!!
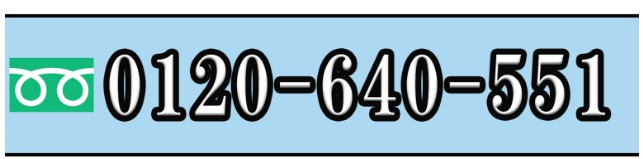 無料で現地調査、見積りを行います。
無料で現地調査、見積りを行います。
年中無料、8:00から20:00 フリーダイヤルでお気軽にご相談下さい。
(福岡県全域、山口県西部、佐賀県東部)
駆除後にやるべき再発防止対策
コウモリを無事に追い出した後も、安心はできません。そのまま放置しておくと、また別のコウモリが戻ってくる可能性があります。
そこで重要になるのが「再発防止対策」です。一度住みつかれた家は再侵入のリスクが高く、しっかりとした対処が必要です。
侵入口の封鎖は最優先
コウモリが侵入できるすき間は意外と小さく、わずか2cmほどの穴があれば入り込めてしまいます。そのため、駆除後は屋根裏・換気口・シャッターまわり・外壁のひび割れなど、家全体の点検が必要です。
侵入口をふさぐには、金網やパンチングメタルを使用すると丈夫で効果的です。
目立たせたくない場所には、コーキング剤やシーリング材を使って見た目も配慮しながら対策するのがおすすめです。とくにベランダやエアコンの配管まわりは見落としがちなので注意しましょう。
定期的な点検と清掃のすすめ
一度封鎖しても、経年劣化や強風などで隙間が再発することがあります。
半年〜1年に一度は、屋根まわりや外壁などを点検し、異常がないかチェックしましょう。とくに木造住宅は小さな穴ができやすいため、点検を習慣化することが大切です。
また、コウモリの糞が残っていると、ニオイで再び寄ってくることもあるため、徹底的な清掃・消毒も忘れずに。天井裏など手が届きにくい場所は、専門業者に依頼するのも一つの手です。
コウモリが好む環境を作らない
コウモリは暗くて静かで、安全な場所を好みます。つまり、家の周辺に「人の気配がなく」「明かりも少ない」場所があると、住みつきやすいのです。
定期的に家の周囲を掃除して人の気配を残す、夜間は屋外照明を点けるようにするなど、ちょっとした工夫で予防効果が高まります。観葉植物や物置の陰なども、定期的に片付けておくとよいでしょう。
再発防止の鍵は、「コウモリがここに戻りたくない」と思う環境を作ることです。少しの手間をかけることで、快適な生活を守ることができます。
コウモリに関するよくある質問
コウモリについては、見かけることが少ないぶん、いろいろな疑問を持っている方も多いようです。ここでは、よくある質問に対して、できるだけわかりやすくお答えしていきます。
コウモリはゴキブリを食べるって本当?
はい、一部のコウモリはゴキブリなどの昆虫を食べる種類もいます。
日本に生息する「アブラコウモリ(イエコウモリ)」もそのひとつで、蚊や蛾、小さな虫などを空中で捕まえて食べています。
家のまわりでゴキブリが減ったように感じる場合、それはコウモリが活動している影響かもしれません。
とはいえ、「だからいてくれてもいい」という考えは危険です。先に紹介したとおり、糞尿や健康被害のリスクがあるため、家に住みつかれるのは避けたほうがよいでしょう。
日本にいるコウモリは危険なの?
日本に生息するコウモリの多くは小型で、性格もおとなしいため、人に襲いかかることはほとんどありません。しかし、病原菌やダニ、ノミを持っている可能性があり、決して安心はできません。
特に、触ったり噛まれたりすると、感染症のリスクがあるため、見つけてもむやみに手を出さないようにしましょう。屋根裏や換気口にいる場合は、専門業者に相談するのが安全です。
コウモリの鳴き声や活動時間は?
コウモリは夜行性の動物です。夕方から夜にかけて活発に動き回り、高い音の「キュッキュッ」というような鳴き声を発することがあります。
この鳴き声は人間には聞こえにくい周波数であることも多いため、「屋根裏からカサカサと音がする」という形で気づくケースも多いです。
もし夜になると毎晩決まった時間に物音がするようであれば、それはコウモリの可能性があるかもしれません。鳴き声や物音のパターンをチェックすることで、早めの対応ができるきっかけにもなります。
まとめ|早めの対処が被害拡大を防ぐ
コウモリの被害は、最初は「ちょっとした音」や「フンが落ちている」といった小さなサインから始まります。
しかし放置していると、家の構造や健康への影響がどんどん深刻になってしまう可能性があります。
被害を防ぐには、「駆除・予防・法律への理解」の3つを意識して対応することが大切です。無理に自分で対処しようとせず、まずは被害の程度を冷静に見極めましょう。
少しでも不安を感じたら、専門業者への相談がおすすめです。プロの知識と経験を活用すれば、安全に、そして確実にコウモリを遠ざけることができます。早めの行動が、家と家族の安心を守る鍵になります。
★コウモリ駆除を業者に頼むなら、あい営繕にお任せ!!★
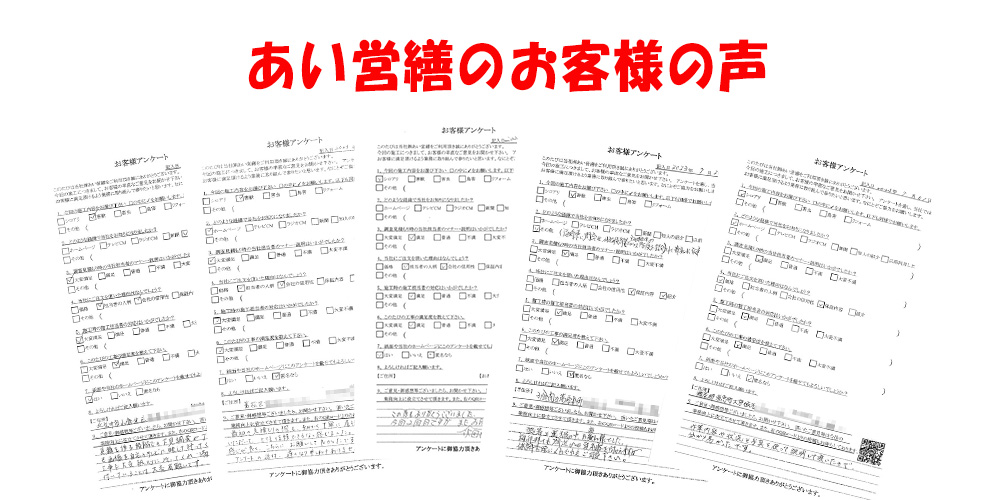
あい営繕を使って、コウモリ駆除をしたお客様の本当の声
👷♂️ 先日はコウモリ駆除でお世話になりました。見積りの担当者、工事の担当者の方々、とても感じの良い方々でした。
😄 大変お世話になりました。仕事のスピードの早さには 驚きました。
🧾 実務工数から計算すると、決して安い金額ではないが、特殊技術・保証期間等から納得した。
📞 貴社に電話したところ、対応の早さに誠意を感じ、即、お願いしました。
🏠 屋根裏の状況をテレビで見ることが出来、大変分り易かったです。
これらは、実際にアンケート用紙に書かれている文言です。
あい営繕の口コミ →
株式会社あい営繕は、公益社団法人ペストコントロール協会加盟業者・公益社団法人日本しろあり対策協会会員です。

弊社ご提案の作業を実施した場合に限らせていただきます。
5年保証!!

シロアリ駆除依頼はあい営繕へ!
相見積もりも大歓迎です。
駆除技術協会の正会員!

コウモリ駆除!自分でやる方法と駆除事例のご紹介
 コウモリ追い出す方法!~自分でやるならこの手順で~
コウモリ追い出す方法!~自分でやるならこの手順で~
現在コウモリの被害に悩まされている方は、どうやってコウモリを追い出してやろうか四苦八苦しているのではないでしょうか。業者に頼むか、自分でやるか、どんな道具を使って追い出すか、色々な選択肢があると思います。
 コウモリが部屋に入ってきたら?確実な追い出し方法と再発生を防ぐ対策を徹底解説
コウモリが部屋に入ってきたら?確実な追い出し方法と再発生を防ぐ対策を徹底解説
こんにちは。コウモリ駆除の専門業者、株式会社あい営繕です。この記事では、部屋にコウモリが入ってきたときの具体的な対処方法と、再発生を防ぐための効果的な対策を詳しく解説します。今日は「コウモリが部屋に入ってきたら!?」というテーマでお話しします。
 シャッターにコウモリ?出入り口の確かめ方と駆除方法を業者が解説
シャッターにコウモリ?出入り口の確かめ方と駆除方法を業者が解説
こんにちは。株式会社あい営繕です。今日は「コウモリとシャッター」についてお話しします。シャッターの下や周りに、茶色・黒の糞みたいなものが落ちているのをみたことはありませんか?それはもしかしたらコウモリの糞かもしれません。
 【北九州市】八幡東区にてコウモリ駆除|被害例と対策をプロが紹介
【北九州市】八幡東区にてコウモリ駆除|被害例と対策をプロが紹介
コウモリを駆除するといいますが、法律で駆除することを禁止されている保護動物だということを知っておいてください。北九州市八幡東区でも同様です。コウモリはゴキブリなどの害虫を食べてくれる益虫でもあります。でも、一方でコウモリが残す糞や尿により建物が汚されたり匂いを発するようになってくるとそうは言っておられません。
 【北九州市】コウモリ発生個所【侵入場所と原因】が分かる
【北九州市】コウモリ発生個所【侵入場所と原因】が分かる
北九州市八幡東区のお客様よりコウモリ駆除のご依頼でした。駆除と言ってもコウモリは鳥獣保護法で保護動物となっていますので殺すことは出来ません。作業は追い出して侵入してこないように穴を塞ぐという内容になります。コウモリの侵入口は何処なのか?何処を伝ってきているのかを細かく見て調べていきます。クーラー周辺ですから範囲は限られてきます。
 コウモリ駆除の業者はどう選ぶ?費用相場や業者のメリットも紹介
コウモリ駆除の業者はどう選ぶ?費用相場や業者のメリットも紹介
「どこの業者にコウモリ駆除をお願いしたらいいか分からない」「駆除業者の費用相場が分からない」「業者にお願いしたいけど、ボッタクられそうで怖い」コウモリ駆除に関して、上記のようなお悩みはありませんか?せっかくなら優良業者にお願いしたいし、詐欺にも引っかかりたくありませんよね。


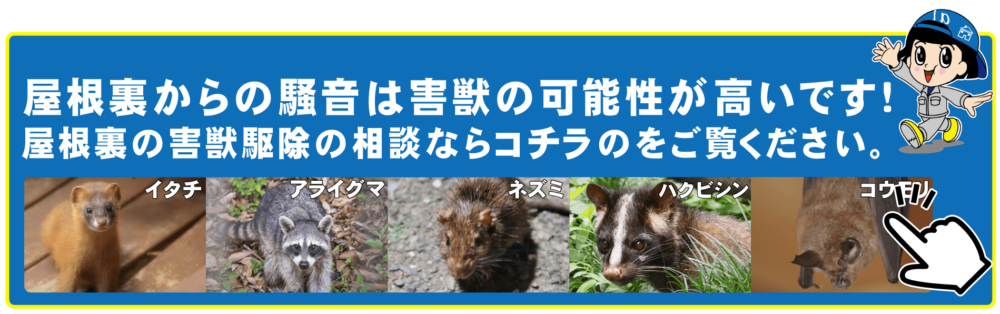
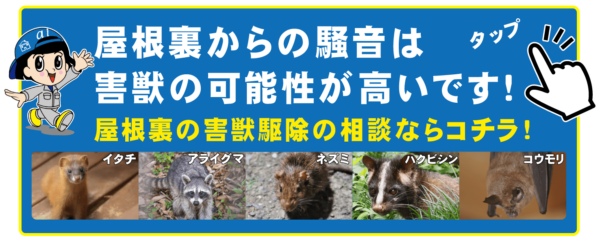
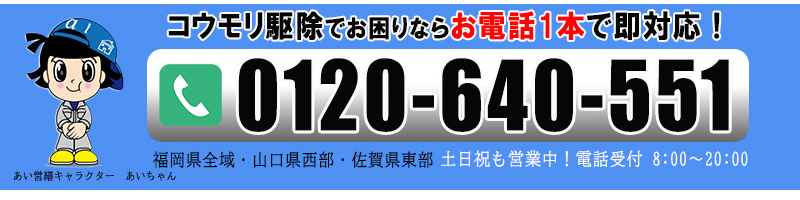











 LINEで無料相談
LINEで無料相談