
アライグマとタヌキは、ぱっと見ではとても似ているため、同じ動物だと思っている人も多いかもしれません。
しかし、実際にはこの二つの動物はまったく異なる種類です。生物学的な分類も異なり、それぞれ違った特徴や生態を持っています。
見た目で判断する場合、しっぽの模様や顔の形、耳の大きさなどに注目すると、比較的簡単に見分けることができます。
また、行動や生息環境にも違いがあるため、知っておくとより確実に区別できるでしょう。
本記事では、アライグマとタヌキの違いについて、特徴や生態をわかりやすく解説します。
これを読めば、山や公園などで見かけたときに、「これはアライグマかな?それともタヌキ?」と迷うことがなくなるはずです。
記事のポイント
● アライグマとタヌキの見た目の違いを理解できる。
● しっぽや顔の模様、足の形で見分ける方法を知ることができる。
● アライグマの生態や害獣指定の理由を学べる。
● 被害が発生した際の対処方法を理解できる。
アライグマとタヌキの基本情報
アライグマとタヌキは見た目が似ているため、混同されがちですが、生物学的にはまったく異なる動物です。
アライグマはアライグマ科に属し、タヌキはイヌ科に分類されるため、犬に近い存在といえます。それぞれの体の特徴や習性を知ることで、より正確に見分けられるようになります。
ここでは、アライグマとタヌキの基本情報を紹介します。
アライグマの基本情報
アライグマは北アメリカ原産の動物で、日本では特定外来生物に指定されています。ペットとして輸入されたものが野生化し、現在では各地でその姿が確認されています。
- 学名:Procyon lotor
- 分類:アライグマ科アライグマ属(イヌ科ではない)
- 体長:50〜100cm
- 体重:4〜10kg
- 寿命:野生では5年ほど、飼育下では15年ほど生きる
特徴
アライグマは目の周りに黒いマスク模様があるのが特徴です。この模様は夜行性の動物によく見られるもので、光を吸収しやすくすることで視界を確保する役割があるとされています。
また、長いしっぽには黒と茶褐色のしま模様があり、これもアライグマ特有の見た目を形作っています。
指が長く、手のように器用に使うことができるため、ドアを開けたり、エサを掴んで食べたりする姿がよく見られます。
一方で、性格はやや攻撃的で、警戒心が強い傾向があります。特に野生のアライグマは、人間に対して敵意を示すことがあるため、むやみに近づかないほうがよいでしょう。
タヌキの基本情報
タヌキは日本各地に生息しており、古くから民話や伝説にも登場するなじみ深い動物です。アライグマと違って日本の自然環境に適応している在来種であり、人里にも頻繁に姿を見せます。
- 学名:Nyctereutes procyonoides
- 分類:イヌ科タヌキ属(実は犬の仲間)
- 体長:40〜60cm
- 体重:3〜10kg
- 寿命:野生では5〜7年ほど
特徴
タヌキの目の周りには黒い模様がありますが、アライグマほどくっきりしていません。全体的にふわっとした毛並みをしており、丸みのあるフォルムが特徴的です。
しっぽは短く、しま模様がないため、アライグマとの大きな見分けポイントになります。また、耳もアライグマに比べると丸く、かわいらしい印象を与えます。
性格は臆病で、人間に対して攻撃的な行動をとることはほとんどありません。しかし、危険を感じると「タヌキ寝入り」と呼ばれる動作をすることがあり、まるで死んだふりをして身を守ることがあります。
ポイント
アライグマとタヌキは見た目が似ていますが、分類上はまったく異なる動物です。
アライグマはしま模様の長いしっぽと器用な前足を持ち、やや攻撃的な性格をしています。
一方、タヌキは黒い模様のある丸い顔と短いしっぽを持ち、性格もおとなしく、臆病な一面があります。
この違いを知っていれば、山や公園で見かけた際にどちらの動物なのかを見分けることができるでしょう。今後、どちらかの動物を見かけたら、ぜひしっぽや顔の特徴をチェックしてみてください。
アライグマとタヌキの見た目の違い
アライグマとタヌキは、遠目から見るとよく似ていますが、しっぽや顔の模様、体型などをよく観察すると、はっきりとした違いがあることがわかります。
それぞれの特徴を押さえておけば、一目で判別することも可能です。ここでは、見た目の違いを詳しく解説します。
しっぽの違い
アライグマとタヌキを見分ける最も簡単な方法の一つが、しっぽの模様です。
-
アライグマのしっぽ
アライグマのしっぽは長く、黒と茶褐色のはっきりとしたシマ模様が特徴的です。このシマ模様は個体ごとに多少異なりますが、一般的には5〜10本の黒い帯が交互に入っています。しっぽは太く、ふさふさとしており、木登りの際にバランスを取る役割も果たします。 -
タヌキのしっぽ
一方、タヌキのしっぽはアライグマに比べると短く、シマ模様はありません。全体的に黒っぽい色をしており、毛がもこもことした印象を与えます。タヌキは地上での生活が中心のため、しっぽの長さが短くても問題なく過ごせるのです。
顔の違い
顔の模様も、アライグマとタヌキを見分けるポイントになります。
-
アライグマの顔
アライグマの顔には、目の周りに黒いマスク模様があります。この模様は非常にくっきりしており、まるでアイマスクをしているかのように見えます。また、鼻筋がやや長めで、シュッとした印象を与えます。さらに、白く長いヒゲが目立ち、表情がどこか鋭く感じられるのが特徴です。 -
タヌキの顔
タヌキの顔にも黒っぽい模様がありますが、アライグマのように明確なマスク模様ではなく、ぼんやりとした印象です。目の周りの黒い部分も、アライグマほどはっきりとしていません。また、鼻筋が短く、顔全体が丸みを帯びているため、柔らかい印象を与えます。ヒゲも短く、白く目立つことはありません。
体の大きさと形
体のシルエットにも大きな違いがあります。
-
アライグマの体型
アライグマはがっしりとした体型をしており、体長は50〜100cmほどになります。手足が長く、前足を使って器用に物を掴むことができるのも特徴です。動きも活発で、木登りやフェンスをよじ登る姿がよく見られます。 -
タヌキの体型
タヌキはアライグマに比べるとずんぐりとした体型をしています。体長は40〜60cmほどで、足が短いため、地面を這うように歩く姿が特徴的です。毛がふわふわしているため、実際よりもふっくらとした印象を受けます。
耳の形の違い
耳の形にもそれぞれ違いがあります。
-
アライグマの耳
アライグマの耳はやや大きく、先が尖っています。耳の周りには白い毛が生えており、遠くから見ても輪郭がはっきりとしています。この白い毛は、暗闇でも視認しやすい特徴の一つです。 -
タヌキの耳
タヌキの耳は丸く、全体的に黒っぽい毛に覆われています。アライグマほど耳が目立たないため、体の丸いフォルムと相まって、かわいらしい印象を与えます。
ポイント
アライグマとタヌキは見た目がよく似ていますが、細かく観察すると、しっぽ、顔、体型、耳の形などに明確な違いがあります。
- しっぽの違い:アライグマはシマ模様があり長い。タヌキは短くて黒っぽい。
- 顔の違い:アライグマはくっきりした黒いマスク模様。タヌキはぼんやりとした黒い模様。
- 体の形:アライグマはがっしりしていて活発。タヌキはずんぐりむっくりしている。
- 耳の違い:アライグマの耳は尖って白い毛が目立つ。タヌキの耳は丸く黒っぽい。
もし山や公園で見かけたら、これらのポイントに注目して、どちらの動物なのかを判断してみてください。違いがわかると、自然観察がより楽しくなるでしょう。
アライグマとタヌキの行動や生態の違い
アライグマとタヌキは見た目だけでなく、生態や行動にも違いがあります。
どちらも雑食性で夜行性ですが、食べるものの好みや生活する場所、行動の仕方にはそれぞれ特徴があります。ここでは、夜行性の違い、食性、足の形、住む場所について詳しく解説します。
夜行性の違い
-
アライグマの夜行性
アライグマは完全な夜行性です。昼間はほとんど活動せず、夜になるとエサを探して動き出します。特に都市部ではゴミを漁る姿がよく見られます。これは、アライグマが手先が器用で、ゴミ箱を開けたり、人間の出した食べ物を簡単に取り出せるからです。 -
タヌキの夜行性
タヌキも基本的には夜行性ですが、昼間に活動することもあります。特に、冬場などは日中に日向ぼっこをしている姿が見られることもあります。また、人間の住む地域に適応しやすいため、住宅街でも目撃されることがあります。
食性の違い
-
アライグマの食性
アライグマは雑食性で、何でも食べることができます。果物や昆虫のほか、魚やカエル、小動物、鳥の卵なども捕食します。さらに、都市部ではゴミ箱を漁り、人間の残した食べ物を食べることもあります。食べる前に水で洗うような仕草をすることがあり、「アライグマ(洗い熊)」という名前の由来にもなっています。 -
タヌキの食性
タヌキも雑食ですが、アライグマとは好みが異なります。ミミズや昆虫、木の実を主に食べ、冬の時期には食料が少なくなるため、落ち葉や草の根を食べることもあります。また、カエルや小動物を食べることもありますが、アライグマほど積極的に狩りをするわけではありません。
足の違い(指の本数)
-
アライグマの足の特徴
アライグマの足は、前足・後ろ足ともに5本指です。特に前足は人間の手のような形をしており、指が長く、器用に物をつかむことができます。そのため、ドアを開けたり、エサを引き出したりすることが得意です。 -
タヌキの足の特徴
タヌキの足は犬に近い形をしており、前足・後ろ足ともに4本指です。アライグマのように物をつかむことはできず、基本的に地面をしっかり踏みしめて歩きます。足跡も犬のような形をしており、アライグマの手形とははっきり違いがあります。
住む場所の違い
-
アライグマの住む場所
アライグマは木登りが得意で、高い場所に住むことを好みます。野生では木の上に巣を作ることが多いですが、都市部では屋根裏や天井裏に住み着くこともあります。手先が器用なので、屋根の隙間から簡単に侵入し、快適な住処を見つけるのです。 -
タヌキの住む場所
タヌキは地面を好み、穴や茂みに隠れて暮らします。自分で穴を掘ることはあまりなく、他の動物が掘った穴や木の根元を利用することが多いです。また、床下や倉庫の隙間など、暗くて狭い場所に住み着くこともあります。アライグマと違って高い場所にはあまり登らず、地面に近い環境で生活するのが特徴です。
ポイント
アライグマとタヌキは、見た目だけでなく行動や生態も大きく異なります。
-
夜行性の違い
- アライグマは完全な夜行性で、昼間はほぼ動かない。
- タヌキは基本夜行性だが、昼間に見かけることもある。
-
食性の違い
- アライグマは何でも食べるが、小動物や魚も好む。
- タヌキは昆虫や木の実を主に食べる。
-
足の違い
- アライグマは5本指で器用に物をつかむ。
- タヌキは4本指で犬に近い足の形をしている。
-
住む場所の違い
- アライグマは木登りが得意で屋根裏や高い場所に住み着く。
- タヌキは地面の穴や茂みに住み、床下に隠れることもある。
これらの違いを知っていれば、どこで見かけたかや、その動物がどのような行動をしているかによって、アライグマかタヌキかを簡単に見分けることができるでしょう。
もし山や公園、住宅街で見かけたら、ぜひ足跡や動きを観察してみてください。
アライグマとタヌキの足跡・糞の違い
アライグマとタヌキは見た目だけでなく、残す足跡や糞の形にも違いがあります。
野生動物の痕跡を観察することで、どちらの動物がその場所を通ったのかを知る手がかりになります。ここでは、それぞれの足跡と糞の特徴を詳しく解説します。
足跡の違い
-
アライグマの足跡
アライグマの足跡は、人間の赤ちゃんの手のような形をしています。前足と後ろ足の両方に5本の指があり、指が長くしっかりと地面に跡を残します。手先が器用なため、指の形がはっきり見えることが特徴です。特に、泥や雪の上ではその特徴的な手形がくっきりと残ることが多いです。また、アライグマは二足歩行に近い動きをすることがあり、足跡の並び方が人間に似ていることもあります。さらに、川辺や水場の近くで発見されることが多く、これはアライグマが水辺を好む習性があるためです。
-
タヌキの足跡
タヌキの足跡は、犬の足跡に似ています。前足・後ろ足ともに4本指で、丸みを帯びた形をしており、花のような模様にも見えます。爪の跡が薄く、アライグマのように長い指の印は残りません。また、タヌキは歩くときに後ろ足を前足の近くに揃えて進むため、足跡が並行に近い形で残ることが多いです。アライグマのように手を広げたような跡はなく、犬やキツネの足跡と見分けがつきにくいですが、より丸みがある点がタヌキの特徴です。
糞の違い
-
アライグマの糞
アライグマの糞は、細長い形をしており、長さは5~18cm程度です。食べたものがそのまま残ることが多く、特に動物の骨や虫の羽、硬い果物の種などが混ざっていることが特徴です。また、アライグマは特定の場所に糞をする「ためフン」の習性があります。これは、同じ場所に繰り返し糞をすることで、自分の縄張りを示す行動と考えられています。そのため、屋根裏やベランダ、庭の隅などに同じような糞が繰り返し見つかる場合、アライグマが住み着いている可能性が高いです。
-
タヌキの糞
タヌキの糞は、アライグマよりも丸みを帯びており、大きさは2~3cmほどです。色は黒っぽく、やや柔らかいことが多いです。タヌキの糞には、果物の種が多く含まれていることが特徴で、これはタヌキが木の実や果物を好んで食べるためです。また、タヌキにも「ためフン」の習性があります。特に山道や林の中では、決まった場所に糞をすることがよくあり、複数のタヌキが同じ場所を使うこともあります。そのため、森の中の小さな土のくぼみや岩の上にまとまった糞がある場合、それはタヌキの仕業かもしれません。
ポイント
アライグマとタヌキの足跡や糞を見れば、どちらの動物がいたのかを判断する手がかりになります。
-
足跡の違い
- アライグマは5本指で、赤ちゃんの手のような形をしている。
- タヌキは4本指で、犬の足跡に似た丸い形をしている。
-
糞の違い
- アライグマの糞は細長く、動物の骨や虫の羽が混ざることが多い。
- タヌキの糞は丸みがあり、黒っぽく、果物の種が含まれることが多い。
また、アライグマもタヌキも「ためフン」をする習性があるため、同じ場所に糞が繰り返し発見された場合は、どちらかが住み着いている可能性があります。
庭や屋根裏などに痕跡を見つけたら、糞の形や足跡をよく観察して、どちらの動物かを見極めてみてください。
アライグマとタヌキ、どちらが強い?
アライグマとタヌキは見た目が似ていますが、性格や行動には大きな違いがあります。特に攻撃性や戦闘能力の面では、両者にははっきりとした差があります。
もしアライグマとタヌキがケンカをしたら、どちらが勝つのでしょうか?ここでは、それぞれの性格や戦闘能力の違いを解説していきます。
アライグマの攻撃力
アライグマは非常に攻撃的な動物です。特に縄張り意識が強く、自分のテリトリーに侵入してきた他の動物や人間に対して、威嚇したり噛みついたりすることがあります。
-
鋭い爪を持っている
アライグマの前足は、まるで手のように器用に使えますが、その先には鋭い爪があり、敵を引っかいたり、しっかりと掴んで攻撃することができます。特に木登りが得意なため、高いところから飛びかかることも可能です。 -
噛む力が強い
アライグマは鋭い歯を持ち、噛む力も強いです。危険を感じると、相手に噛みつき、大きなケガを負わせることがあります。実際にペットとして飼われていたアライグマが飼い主に噛みつく事故も報告されています。 -
勇敢で後退しない
アライグマは、自分より大きな相手にも立ち向かうことがあります。逃げるよりも戦うことを選ぶことが多く、ケンカになった場合、非常に手強い相手になります。
タヌキの防御力
一方で、タヌキは基本的に臆病な性格をしており、戦闘向きではありません。
-
すぐに逃げる
タヌキは危険を察知すると、すぐに逃げる傾向があります。アライグマのように積極的に攻撃することはほとんどなく、できるだけ戦いを避ける行動を取ります。 -
「タヌキ寝入り」をする
タヌキは、身の危険を感じると「死んだふり」をすることがあります。これを「タヌキ寝入り」と言い、相手が興味を失うまでじっと動かないことで身を守る戦術です。 -
戦う武器が少ない
タヌキにも爪や歯はありますが、アライグマほど鋭くなく、攻撃的な性格でもありません。ケンカになったとしても、アライグマのように果敢に立ち向かうことはないでしょう。
結論:アライグマが圧倒的に強い
もしアライグマとタヌキがケンカになったら、圧倒的にアライグマが強いと考えられます。
アライグマは鋭い爪と歯を持ち、攻撃的な性格であるため、戦いになればタヌキに勝つ可能性が高いです。一方のタヌキは、戦うよりも逃げることを選び、最後の手段として「死んだふり」をすることが多いです。
このように、アライグマとタヌキは性格や戦闘能力が大きく異なるため、直接的な争いにはならないことがほとんどです。
もし自然の中で両者を見かけたら、そっと観察し、それぞれの違いを楽しんでみるのも面白いかもしれません。
アライグマとタヌキのハーフは存在する?
アライグマとタヌキは見た目が似ているため、「ハーフの個体がいるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、結論から言うと、アライグマとタヌキのハーフは存在しません。これは、両者が生物学的にまったく異なる種であり、交配ができないためです。
遺伝的に交配は不可能
アライグマとタヌキは分類上、全く別のグループに属しています。
-
アライグマの分類
- 科:アライグマ科
- 属:アライグマ属
- 学名:Procyon lotor
-
タヌキの分類
- 科:イヌ科
- 属:タヌキ属
- 学名:Nyctereutes procyonoides
このように、アライグマはアライグマ科、タヌキはイヌ科に分類され、そもそも遺伝的に大きな違いがあります。生物学的に近い種でなければ交配して子孫を残すことはできません。
そのため、アライグマとタヌキが自然界で交配することはなく、仮に同じ環境で生活していても、繁殖することはありえません。
なぜハーフがいると誤解されるのか?
アライグマとタヌキは、どちらも毛がふさふさしており、顔に黒い模様があるため、一見すると似ています。
特に薄暗い場所や遠くから見ると区別がつきにくく、「もしかしてアライグマとタヌキの混血?」と勘違いされることがあるかもしれません。
しかし、実際には両者が交配することは生物学的に不可能であり、自然界に「アライグマタヌキ」という存在はいないのです。
ポイント
アライグマとタヌキは見た目が似ているため、ハーフがいるのではないかと思うかもしれません。しかし、アライグマはアライグマ科、タヌキはイヌ科と分類が異なり、交配は不可能です。
そのため、「アライグマとタヌキのハーフを見た!」という話があっても、それは単にどちらかの特徴を強く持つ個体だった可能性が高いです。
自然界では、異なる種の動物が混ざることはほとんどなく、それぞれの種として独自の進化を続けています。
もし野生でどちらかの動物を見かけたら、しっぽや顔の模様などの特徴を観察し、どちらなのかを見極めてみるのも面白いでしょう。
まとめ
アライグマとタヌキは見た目がよく似ていますが、しっぽや顔の模様、行動などを観察することで簡単に見分けることができます。ここでは、記事の内容を振り返り、重要なポイントを整理します。
アライグマとタヌキの見分け方のポイント
-
しっぽの模様
- アライグマ:黒と茶色のはっきりしたシマ模様がある
- タヌキ:短くてシマ模様がなく、全体的に黒っぽい
-
顔の模様
- アライグマ:目の周りにくっきりした黒いマスク模様がある
- タヌキ:黒っぽい部分があるが、ぼんやりとしている
-
足の形
- アライグマ:前足・後ろ足ともに5本指で、人間の手のような形をしている
- タヌキ:4本指で、犬の足跡に似た丸い形
-
行動の違い
- アライグマ:木登りが得意で、屋根裏や高い場所に住み着くことが多い
- タヌキ:地面を好み、穴や茂みに隠れて生活する
アライグマは害獣として指定されている
アライグマは日本では 特定外来生物 に指定されており、繁殖力が強く、農作物や家屋に被害を与えることが問題視されています。
さらに、気性が荒く、人間に危害を加えることもあるため、むやみに近づかないほうがよいでしょう。
もし家の周りでアライグマによる被害が発生した場合、 害獣駆除の専門業者 に相談するのが最適です。専門家に依頼することで、安全に対処できます。
一方、タヌキはもともと日本に生息する在来種であり、そこまで積極的に駆除されることはありませんが、都市部に適応しやすいため、ゴミを漁ったり人家の床下に住み着いたりすることもあります。
総括
アライグマとタヌキは似ているようでいて、多くの違いがあります。しっぽの模様や顔の特徴、足の形を見れば、どちらの動物かを判断することができます。
自然の中でアライグマやタヌキを見かけたときには、本記事で紹介した見分け方を活用して、どちらの動物か観察してみてください。
また、もしアライグマによる被害が発生した場合は、適切な対策を取り、安全に対応することをおすすめします。
「あい営繕」のお客様:屋根裏動物駆除の口コミ
口コミ
実家のイタチ駆除で沢山ある業者の中から何処にしたら良いか悩んでいた時、友人の親戚がアライグマの駆除をあい営繕さんでお願いした話を聞き、紹介していただきました。 早速電話をするとその日のうちに調査、見積もりをしていただき、状況を画像を見ながら詳しく説明していただきました。金額も高額な事は承知していましたが、納得の上でお願いする事にしました。
口コミ
北九州市若松区にてコウモリ駆除して頂きました。 約1週間の施行期間にて、コウモリの追い出し、フンの片付け、侵入口の封鎖、断熱材の交換、殺菌消臭等を行ってもらいました。費用は少々掛かりましたが害獣駆除など自分で出来るわけもないので、依頼して良かったと思います。
口コミ
知り合いの方から、あい営繕さんのことを知り電話をしたところ、受付の女性が、こちらの状況を大変丁寧に聞いて下さって、ひとまず安心な気持ちになりました。 調査の方も、正確な間取り図を描き家の外回りと内と隅々まで調べてくれアライグマとイタチの侵入口を見つけてくれました。
口コミ
イタチ駆除でお世話になりました。古い家で対応に手間がかかり面倒だったと思いますが、汗だくになり施工していただき感謝しています。イタチには長年悩まされていましたが、相談した建設会社さんから専門家に相談した方が良いと言われ色々調べてあい営繕さんを知りました。見積りをお願いするのもかなり不安がありましたが、すぐに社長さんから連絡があり、見積りや検討時間とこちらの都合に合わせて対応していただき、予想より高額にはなりましたが加盟団体や資格、保証内容からお願いすることにしました。終わって保証書もいただき、何かあれば安心してまたお願いできると思っています。施工後たまにコトコトと音がしていますが、侵入される事はなく快適に過ごせて、もっと早くにお願いすれば良かったと思っています。
口コミ
アライグマの侵入口封鎖と、天井裏の殺虫、除菌、消臭を対応いただきました。 夜中に人の足音のような音がしたため始めは泥棒かとおびえてしまいました。外から見たところ、アライグマが屋根の上にいるところをちょうど動画に撮れたため役所に相談。何らかの対策をすることに決め、あい営繕さんにたどり着きました。
口コミ
八幡西区でアライグマ駆除と侵入防止工事をお願いしました。 天井で人がいるような物音が聞こえるようになり、不安に思っていたところ、帰省中の息子があい営繕さんを見つけてくれました。 電話での対応は、社長さんがよく話を聞いて下さり、すぐに調査の方が来て下さいました。細かいところまで丁寧に見て頂き、アライグマがいることがわかりました。
口コミ
小倉南区でアライグマ、イタチの侵入防止工事をお願いしました。家にいると壁伝いに動物の鳴き声が聞こえたり、外の戸袋が荒らされていてそこから天井裏に入ったような痕跡があり不安な日々が続いていたので、まずは見積りをお願いしたのですが、とても丁寧に時間をかけて侵入口の確認、説明をしていただき、見積りしていただきました。
口コミ
とても丁寧で、ご説明もしっかりしていただき、 調査、工事を安心してお任せできました。 家もこれで無事、安心です。ありがとうございました。
口コミ
大変お世話になりました。仕事のスピードの早さには 驚きました。
口コミ
実務工数から計算すると、決して安い金額ではないが、特殊技術・保証期間等から納得した。
口コミ
価格の事はまったく分からないので当初は相見積もりをしょうかと思ってました。 貴社に電話したところ、対応の早さに誠意を感じ、即、お願いしました。
口コミ
屋根裏の状況をテレビで見ることが出来、大変分り易かったです。 あっという間に1Fの図面が出来上り、びっくりしました。 施工担当者も信頼出来ました。
口コミ
見積り、施工とも来ていただいた方皆様とても感じがよく、丁寧に対応やお仕事をしていただいたと思います。 進入口も見つけてふさいでもらって安心しました。 両日と暑い中の作業でしたが、最初と最後のご挨拶をいただくときはきちんと会社のユニフォームに着がえられてとても好感がもてました。 見積もりで来てもらった島村さんには、気にかけていただき施工日に寄ってもらい、本当に1件1件真摯にお仕事されているんだなと思いました。ご近所で同じようなことがあれば、ご紹介できる方々でした。ありがとうございました。
口コミ
先日は、暑い中アライグマ駆除工事で大変お世話になりありがとうございました。 見積り時にカメラで現状を撮って頂き、侵入口や天井裏を実際に見る事が出来、施工後もカメラで収め工事の前後の写真を資料として送って頂きとてもわかりやすかったです。 丁寧に仕事して頂き安心する事が出来ました。
口コミ
酷暑と悪天候の中、お疲れ様でした。 梅雨明けも間近で夏本番を無化ますが、体調管理にくれぐれもご自愛ください。
最後に.
こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。
【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?
最後までお読みいただきましてありがとうございました。

弊社ご提案の作業を実施した場合に限らせていただきます。
5年保証!!

シロアリ駆除依頼はあい営繕へ!
相見積もりも大歓迎です。
駆除技術協会の正会員!


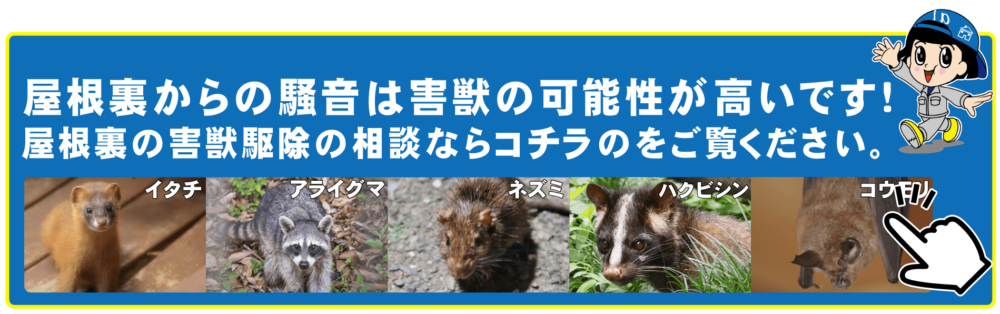
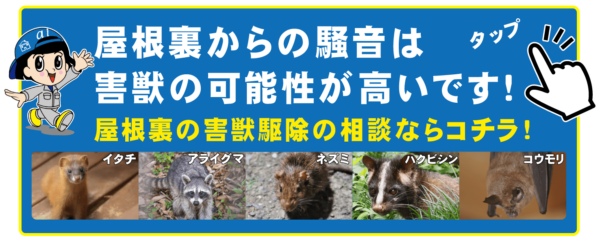
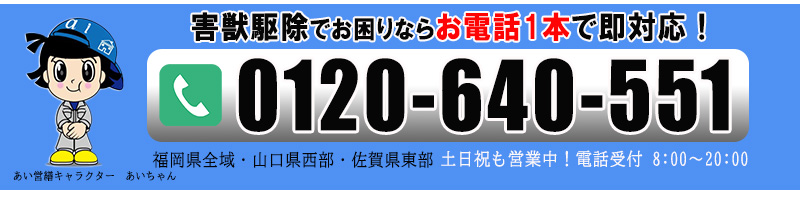




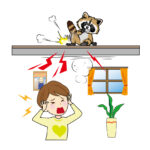








 LINEで無料相談
LINEで無料相談